富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔
歴史と自然−野鳥−山野草木-なんでも館−吉田うどん−クイズ−富士山検定考−ショッピング(広告)
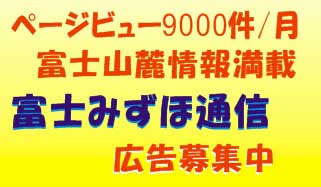
|
富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔 |
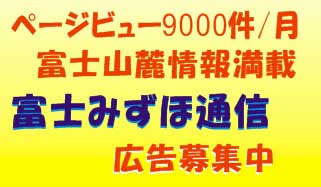 |
|||
| 情報源−過去総目次−リンク−ご挨拶−メール−プライバシーポリシー | ||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 3 中の茶屋、吉田胎内周辺の野鳥や野草 中の茶屋や吉田胎内の周辺はアカマツの林で、富士桜、ウツギなどの低木もたくさんあります。 野鳥も多く、全国で有数の探鳥場所の一つです。山野草も豊富で、自然観察もたくさん行われています。 3−1 野鳥 野鳥は四季を通じて観察できます。 野鳥には四季を通じて同じ地域にいる「留鳥」と秋に渡来して越冬する「冬鳥」、春夏に渡来し秋に帰る「夏鳥」がいます。(この他に日本国内で季節で移動する「漂鳥」、北で繁殖し南で越冬する「旅鳥」の区分があります)富士北麓は標高が高いので、一般的に留鳥と呼ばれていても冬は見られない鳥もいます。留鳥として観察できるのは、ヒヨドリ、ウグイス、シジュウカラ、エナガ、ヒガラ、コガラ、ゴジュウカラ、ヤマガラ、ヤマゲラ、アカゲラ、アオゲラ、コゲラ、セグロセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイ、アカハラ、モズ、メジロ、ホオジロ、ツバメ、キジバト、スズメ、トビ、ノスリ、ハシブトカラス、ビンズイ等です。冬鳥として観察できるのは、ツグミ、カシラダカ、シロハラ、ウソ、シメ、ジョウビタキ等です。夏鳥としてキジ、カッコウ、センダイムシクイ、メボソムシクイ、イカル、オオルリ、コルリ、コヨシキリなどが観察できます。 (鳴き声は文一出版の「野鳥図鑑」による。()は(撮影地)) 「ケッケッケッ」(吉田胎内)
木の上に集団でいることもある「キョキイキョエ」(雁の穴)
(新倉浅間神社)
すぐ近くで鳴いているのにどこだか分からないことが多い。 (河口湖)
(竜ヶ丘)
(創造の森)
(河高近く)
この写真は3合目のもの、似ている鳥にセンダイムシクイがいる。こちらは「チィーチョチョヂー」と鳴き「焼酎一杯グイー」と聞きなされる。中の茶屋ではセンダイムシクイが多いのかも知れない。
ツツピーと鳴いたらシジュウカラ「ツピーツピーツピー」 (山中湖)
「チョチョ ツチーチョチョツ ツイツイツイ・・・」 (滝沢林道)
「チョチ チチョ チュリリーチチョ」「一筆啓上仕り候」と聞きなされる。 (鳴沢)
「クイックイッ」「キュウキュウ」 (下の水)
「ツツピーツツピーツツピー」 (創造の森) この中の多くは富士吉田市等の市街地でも観察できます。 鳴き声は繁殖期に雄が鳴く「さえずり」と「さえずり」以外の「地鳴き」があります。 ウグイスの有名な鳴き声「ホーホケキョ」は「さえずり」です。 野鳥の容姿は雄と雌で大きく異なります。一般的に雄が派手で雌が地味です。 中の茶屋の周辺はアカマツやカラマツの背が高いので、梢の上で鳴く野鳥は双眼鏡が必要です。また、藪の中で鳴く鳥は、姿を見ることが難しいです。キツツキ類は木の途中に止まるので観察が容易です。カラ類は低木や枝に止まるので良く見ることができます。新緑から盛夏の季節は葉が多く蝉の声がやかましいので野鳥観察には不向きです。吉田胎内近くの沢は野鳥を下に見ることができるので観察場所としては向いています。環境科学研究所、フィールドセンターには野鳥観察用のコーナーがあり、窓の外の野鳥を間近に見ることができます。 家の周りにどんな鳥がいるか観察してみましょう。 日記のように日付をつけて何種類の声を聞いたか、また見たかメモしてみましょう。名前が分からなくても聞いた特徴をメモして見ましょう。家の周りでも10種類ぐらいはいると思います。 見たときは、大きさをスズメ、ヒヨドリ、カラスなどと比較して大きいか小さいかを比較すると面白いです。鳴き声は色々ですし、鳴きまねをする鳥もいます。もちろん、中の茶屋周辺でも同じようにメモをとって、来年、今年と比較してみて下さい。段々と野鳥が身近になると思います。 3−2 樹木と野草 A 樹木 中の茶屋周辺の樹木はアカマツ、カラマツ、マメザクラ(フジザクラ)、ヤマツツジ、ミツバツツジ、ヤブウツギ、ミズキ、ヤマハンノキ、コナラ、ミズナラ、ハナイカダ、バッコヤナギ、モミジイチゴ、シモツケ、ボケ、バライチゴ、ヤマブキ、フジイバラ、ミヤコザサ、チョウセンゴミシなどです。吉田胎内周辺ではアセビ、ソヨゴ、ダンコウバイ、ツリバナ、ウリハダカエデ、リョウブ、フジが見られます。 木の種類は外観で見分けることができますが、葉の形や色にも特徴があります。 例えば笹を見ると富士北麓には点々と笹が群生しています。中の茶屋北側の沢にも小さな群落があります。これらの笹は背が低く、冬、笹の葉の両側が白く枯れるクマザサです。クマザサは冬に葉の周辺が枯れて白いふち(隈)がでるのでクマザサと呼ばれるとか、熊のいそうな場所に生えるのでクマザサと呼ばれています。 一方、鳴沢口登山道長尾山周辺には勝山村の特産、竹細工の原料となるスズタケの群落があります。吉田市内の家庭などに見られる背の高い竹は多くがモウチクトウです。(竹はイネ科に属し、竹や笹は670種もあると言われています。静岡県の長泉町には富士竹類植物園があります。)葉以外でも木の肌に特徴のある場合は、それだけで見分けられるものがあります。リョウブの木肌は白と薄茶のまだら模様 ツリバナはついた実が葉の付け根付近から柄が下を向いて伸び数個の黒の実に赤い帽子をかぶったような実をつけます。(写真左)
フジザクラ:マメザクラの別名。富士山や箱根などの火山地帯に分布する。富士吉田市の花に指定されている。毎年4月末から5月の連休頃満開となる。富士吉田市では中の茶屋で富士桜祭を、河口湖町では創造の森で富士桜とミツバツツジ祭を開催している。(右は中の茶屋の富士桜) 下の樹木の特徴をメモしてみましょう。 どのような場所にあるのか、背が高いのか低いのか、全体の形はどうかなど思いつくままメモしてみましょう。 木の名前 観察メモ(図鑑を見て実際の木を確かめて見ましょう) アカマツ、カラマツ、マメザクラ(フジザクラ)、ヤマツツジ、ミツバツツジ、ヤブウツギ、ミズキ、 ヤマハンノキ、コナラ、ミズナラ、ハナイカダ、バッコヤナギ、モミジイチゴ、 シモツケ、ボケ、バライチゴ、ヤマブキ、フジイバラ、クマザサ、ミヤコザサ、 チョウセンゴミシ、アセビ、ソヨゴ、ダンコウバイ、ツリバナ、ウリハダカエデ、 リョウブ、フジ B 野草 春から秋にかけて観察できます。 中の茶屋の周辺で地面に目をやるとスミレが咲き、少し林の中に入ると、巨大なサークルのオシダに感動します。「富士吉田景観野外博物ランド」(田中収編集)によると「夏にはアヤメ、ヤマハタザオ、ヤマホタルブクロ、ウツボグサ、ダイコンソウ、コバノギボウシ、オオバギボウシ、キンミズヒキ、フタバハギ等、秋にはゲンノショウコ、ハンゴンソウ、アキノキリンソウ、ノコンギク、シシウド等の花が見られます。他にオオケタデ、イタドリ、シオデ、ヤマウルシ、ネノブキ、ウド、ヘビノネゴザ、アレチマツヨイグサ、シロツメクサ、ツルウメモドキ等の植物が見られます」と紹介されています。 紹介されている以外にもスミレ、フタリシズカ、ミズヒキ、シロバナノヘビイチゴ、ワチガイソウ、ツマトリソウ、マイズルソウ、オカトラノオ、イヌタデ、ツリフネソウ、キツリフネ、シデシャジン、ツリガネニンジン、タケニグサ、クサコアカソ、セイヨウタンポポなども見ることができます。また、オシダなどシダ類やコケ、きのこなどたくさんの植物を観察できます。 下の花はいつ頃見た花でしょう、どんなところ(日当たりとか日陰など)に咲いている花でしょう。
釣鐘を吊るしたような形から名前がつけられたのでしょうか?
棒のアイスを突き上げて並べたような壮観な景色ができます。 ショウマと呼ばれるものには他にトリアシショウマ、レンゲショウマ、などがあり、トリアシショウマに似ている形の花にチダケサシがある。
マイヅルソウ 小さくてかわいい花です
妻をとられてしまいそうな怖い名前ですが、実際は日陰に生える可憐な花です。どうしてこんな名前がついたんでしょうね。 ウバユリ オシダ この群落は異次元の世界を見るようです。 まだまだたくさんの野草があります。 花の名前は難しいものもありますが、特徴を探すなどして楽しめばよいでしょう。 ちょっとした野草の雑学
(左の写真が岩殿山のカントウタンポポ)
(この項は多分に大宮の私見ですので、各自ご確認下さい。) アヤメ:「いずれアヤメかカキツバタ」と諺にある。ノハナショウブ、アヤメ、カキツバタの区別は知っておきたい。尾垂山の中腹、忠霊塔の上にアヤメの群生地が育成されている。 ノハナショウブ:葉の中央を縦に通る中脈が大きく隆起している。花菖蒲はノハナショウブの園芸種。朝霧高原に菖蒲を集めた菖蒲園が開園している。 カキツバタ:アヤメの葉の幅が1cm程度に対してカキツバタは3cm程度と広い。アヤメの花びらの付け根部分には黄色と紫の網状の斑があるが、カキツバタは黄色い一本の筋のみ。アヤメは花が葉より高い位置に咲くが、カキツバタは葉の先端が花より高い。 月見草:太宰治の小説で「富士には月見草がよく似合う」と言うくだりで有名。これは、オオマツヨイグサの別名。上の「アレチマツヨイグサ」は花が小さいメマツヨイグサの一種。メマツヨイグサ、オオマツヨイグサの両方とも明治以降渡来し広がった外来種。 (植物の項参考:角川書店入門歳時記、山と渓谷社日本の野草) 3−3 動物 大型哺乳類では、タヌキ、キツネ、ウサギ、シカ、テンなどがいる 中の茶屋より少し上に入った富士林道でキツネを目撃しました。また、天神山のスキー場へ行く途中で夕方鹿と衝突しそうになったことがあります。中の茶屋下から船津胎内へ道路が整備され、林道も滝沢林道、富士林道と舗装道路網が整備され車社会は山頂へ向かって広がっています。小動物にとって住みにくい場所になっていると思います。人間の近くにいて、食を同じくする猿やカラスなどが多くなっています。(右は新芽?を食べる鹿:滝沢林道) 私の疑問は富士山麓に猿はいないと言われていることです。 つい最近も旭町に猿がでました。(写真右) 本当にいないのでしょうか。猿が食べるような食物が無いのでしょうか。 と、一人疑問に思っています。 3−4 昆虫 蝉は初夏になるとハルゼミが鳴き始めます。松林を離れると急に鳴き声は遠くなります。別名マツゼミと呼ばれるように松林を好む蝉です。ミンミンゼミ、ヒグラシも声が聞こえます。ハチやクモ、チョウやガもたくさんの種類が観察できますが、残念ながらまとめた資料がありません。 とりあえず羅列します。 チョウ、昆虫など
本物を探してみて下さい。 右は抜け殻ですね。 おわりに 「富士吉田景観野外博物ランド」(無料配布物で現在絶版、富士吉田市立図書館にあると思います) 「御山登り道」(富士吉田市教育委員会販売中、1400円) 「富士を知る」(本屋で販売中1900円) 完 |
||||||||||||||||||||
| ↑頁トップへ 富士北麓−瑞穂通信=富士みずほ通信 http://www.fjsan.net | ||||||||||||||||||||