富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔
歴史と自然−野鳥−山野草木-なんでも館−吉田うどん−クイズ−富士山検定考−ショッピング(広告)
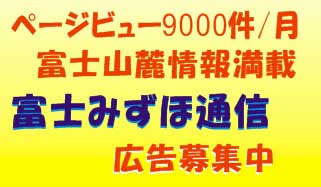
|
富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔 |
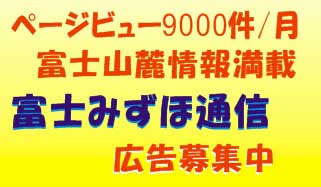 |
|||
| 情報源−過去総目次−リンク−ご挨拶−メール−プライバシーポリシー | ||||
| 風呂屋の富士山を再現(in富士吉田、野ばら) 町田忍氏がスライドトーク、銭湯絵師 中島盛夫氏が銭湯の富士山を再現 |
|||
風呂屋の富士山と言ってもピンとくる人が少なくなっているのではないだろうか。 昭和48年大流行した「神田川」にはこんな歌詞があった。「赤い手拭いマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋」当時は銭湯、すなわち外風呂が当たり前で、彼女との淡い初恋を思い出す場面としても登場する代表的なシーンに銭湯があった。昭和が平成に変わり早17年、あっという間に昭和が遠くなってしまい、今やアパートという言葉も死語に近く、学生でもワンルームマンションが当たり前の世の中、バスルームのないマンションなんて考えられなーい。なんて時代である。都内でも銭湯が1000軒を割ってしまったと聞いている。 平成に年号が変わったことと、銭湯の数とは何の関係もないと思うが、昭和の代表的なイメージの一つに銭湯があり、平成の今、それが失われつつある。そんな意味で銭湯は昭和の時代を映す遺産なのだろう。まして、その銭湯の中に描かれていた銭湯絵は、銭湯の番台と同じように、昭和の時代を映すものの一つなのだろう。 大宮はこの銭湯絵の富士山にも高い関心を持っていた。関心といっても、研究対象のような崇高な関心ではなく、ただただ、収集心から手に入れたいと思っていただけなのだが。(銭湯の絵を集めることは不可能だが、写真は可能だ。しかし、営業中にシャッターは難しい。そんな訳で足ふみしていた。) そんなチャンスに、思いがけず富士吉田市内で出会うことが出来た。平成17年富士吉田市内で開かれた「まちがミュージアム」の一環として「風呂屋の富士山」を再現するイベントが開かれると言うではないか。しかも、土曜日。早速チケットを申込み会場に向かった。 会場は富士吉田市内の喫茶店「野ばら」2階。2005年9月10日午後1時30分。イベントは風俗研究者では第一人者の町田忍氏が銭湯の歴史などについてスライドトークし、あわせて銭湯絵師 中島盛夫氏の銭湯の富士絵描画実演があると言う。(右写真:製作途中の富士山絵前で町田氏(右)と中島氏) イベントの前のコーヒータイム 「野ばら」の2階は普段地元の絵画グループが発表会などに使っている。30人程度入ると一杯になる会場だ。もし、大勢来て入れなかったら、折角の絵が見れなくなってしまう。そんな心配から、少し早く会場に入った。ところが、誰もいない。会場には折りたたみいすが並べられて、前面に富士山を描く畳4畳程の大きなキャンパスが準備されていた。壁には小さな富士山のペンキ絵が飾られていた。照明がついていないので薄暗くシーンとしていた。拍子抜けした気分で、下の「野ばら」でコーヒーを頼んだ。「係の人がいるはずですが」マスターは怪訝な風で応えた。とりあえず待ってみることにしてコーヒーを口にした。喫茶店の客は私1人だ。学生時代良く喫茶店で時間をつぶしていた。ほんの数分なのだが、そんな時代を思い起こした。しばらくすると見慣れた顔のS氏が入ってきた。S氏は前の前の会社の先輩だ。「どうしてここに・・」「まさか手伝いですか?」その通りだった。S氏はイベントの手伝いをしていた。「町田さんなら上に来ているよ。行ってごらん」先輩に促されて、残ったコーヒーを一気に飲み、2階に上がった。まだ誰も居ないと思ったが、隅に静かに町田氏が座っていた。町田氏とは初対面であるが、前の会社のOさんを通じて紹介されていたので、なんとなく少し知り合いのようにお話させていただいた。写真撮影のOKももらった。そうこうしている内に、人が増えてきた。銭湯絵師中島盛夫氏もお見えになった。会場には遠く東京や仙台から来たお客さんもいた。最近はテレビ出演も多い町田氏ファンなのか、銭湯絵の中島ファンなのか、それとも、最近毎年続いている「まちはミュージアム」のファンなのかさだかでないが、若い人も多かった。地元の絵のグループのメンバーも来ていた。計ったように椅子席が埋まった。町田氏が挨拶し、イベントがスタートした。 スライドトーク スライド  になにやら工事現場のような写真が映し出された。風呂屋を取り壊している写真だ。町田氏が銭湯めぐりを始めたきっかけとなったスライドだ。次に銭湯の歴史が「柘榴口」のスライドなどで紹介され、おどろくことに霊柩車の話に発展して行った。もともと銭湯が仏教の普及を図り、お寺で始まったことなど、銭湯と、お寺と霊柩車と興味深く絡んで行く様子が紹介された。その中で銭湯絵としてペンキ絵、タイル絵、ガラス絵などが紹介された。しかし、今思い起こすと、スライドで紹介されたことを良く覚えていないことが多い。最近物覚えが悪くなったためなのか、興味がペンキ絵に集中していたのか良く分からない。そんな訳で話題を次の中島氏のペンキ絵に移す。(1994年初版と言うことは今から10年以上前になるが「風呂屋の富士山」が出版された。今回の霊柩車の話は出てないが、ペンキ絵についは詳しく紹介されている。もちろん著者は町田氏、そして大竹誠の共著。ファラオ企画、1456円+税、なんと2005年9月24日現在新宿紀伊国屋店頭在庫ありですよ) になにやら工事現場のような写真が映し出された。風呂屋を取り壊している写真だ。町田氏が銭湯めぐりを始めたきっかけとなったスライドだ。次に銭湯の歴史が「柘榴口」のスライドなどで紹介され、おどろくことに霊柩車の話に発展して行った。もともと銭湯が仏教の普及を図り、お寺で始まったことなど、銭湯と、お寺と霊柩車と興味深く絡んで行く様子が紹介された。その中で銭湯絵としてペンキ絵、タイル絵、ガラス絵などが紹介された。しかし、今思い起こすと、スライドで紹介されたことを良く覚えていないことが多い。最近物覚えが悪くなったためなのか、興味がペンキ絵に集中していたのか良く分からない。そんな訳で話題を次の中島氏のペンキ絵に移す。(1994年初版と言うことは今から10年以上前になるが「風呂屋の富士山」が出版された。今回の霊柩車の話は出てないが、ペンキ絵についは詳しく紹介されている。もちろん著者は町田氏、そして大竹誠の共著。ファラオ企画、1456円+税、なんと2005年9月24日現在新宿紀伊国屋店頭在庫ありですよ)ペンキ絵実演 ペンキ絵は真っ白な畳4畳程のキャンパスに一本の横線が引かれて始まった。本来の風呂屋の壁はもっと大きいが、今回はイベント用の特製キャンパスだ。富士山の輪郭が描かれると、ペンキを塗るローラーが持ち出され、あっという間に空が描かれていく。筆が元に戻り、息を継ぐまもなく、雲と富士山の斜面が現れる。早い早い、なんか魔法を見ているようだ。手をかざして横に振ると、純白のキャンパスに富士山や湖が出現するようなイメージだ。しかも、当然だが空は見事に濃い青から淡い青にグラデーションが掛かっているように見える。これは空に雲を適度に配置することによって実現しているようだ。油絵のように何度も何度も書き加えていく手法とは明らかに違う。すばやく書かないと銭湯の営業時間に間に合わない、短時間勝負が生み出したマジック的描画手法だ。山肌も、富士北麓から見た山襞によるひだが殆ど二回程度の筆で完成している。書き直しはない。最近のインクジェットプリンターの出力を見ているようだ。途中で殆ど完成かと思える場面で休憩が入った。 町田氏と中島氏のツーショットをお願いしたら快く応じていただくことが出来た。 休憩の後、仕上げに入った。前景の松、手前に描かれた湖水の対岸にある小山  の上の小屋、湖上に浮かぶ小船、最後に右下に中島氏のサイン。本来の銭湯の背景画にはサインが入らないようだが、今回の絵はサイン入りだ。 の上の小屋、湖上に浮かぶ小船、最後に右下に中島氏のサイン。本来の銭湯の背景画にはサインが入らないようだが、今回の絵はサイン入りだ。完成後、「この絵どこから書いたか分かりますか?」「千円札を持っている人は裏側を見て、比較して見て下さい。」中島氏から、参加者に逆質問がだされた。本当だ。千円札の裏には同じ位置からの富士が描かれていた。今回のペンキ絵は本栖湖からの富士山だった。旧五千円札、新千円札の富士山図の原画は岡田紅陽の本栖湖からの写真だ。本栖湖からの富士山は最も良く描かれる富士山の一つだろう。それが見事に大きなキャンパスに描かれていた。描画時間は正味1時間だった。職人と芸術家が一体となった技のなせるものだ。銭湯数が減少せず、ペンキ絵を描く人がこんなに少なく(平成17年現在3人と聞いた)ならなければ、このように注目されることもなかった画家だろう。歴史の皮肉な側面かもしれない。現在中島氏の描いた富士山などのペンキ絵は家庭のお風呂にかけられる程度の大きさのも  のが作成されて販売されている。当日の会場にも大小二種類のペンキ絵が周囲の壁に展示即売されていた。(東京渋谷の東急ハンズでも置いてあるとの情報で探しに行ったが確認できなかった。) のが作成されて販売されている。当日の会場にも大小二種類のペンキ絵が周囲の壁に展示即売されていた。(東京渋谷の東急ハンズでも置いてあるとの情報で探しに行ったが確認できなかった。)イベント終了後、ライブ終了後の余韻と同じ雰囲気が会場にあった。誰が頼むでもなく町田、中島氏と参加者を囲んで記念写真撮影大会となった。熱く短いキャンパスとの格闘、富士吉田市出身の切り絵師、百鬼丸の路上実演とも重なり、新宿、原宿などの大道芸とも通じるものが感じられた。 会場に大量のバナナがあった。イベントの主役の1人中島氏が持ってきたものだ。氏は現在銭湯絵の仕事がない時は副業として野菜市場に行っているようだが、その関係で参加者にバナナが振舞われた。当日の入場料は町田氏のスライドトーク+中島氏の富士山ペンキ絵実演+バナナ、〆て800円 町田様、中島様そして主催者とスタッフの皆さんお疲れ様でした。 
|
|||